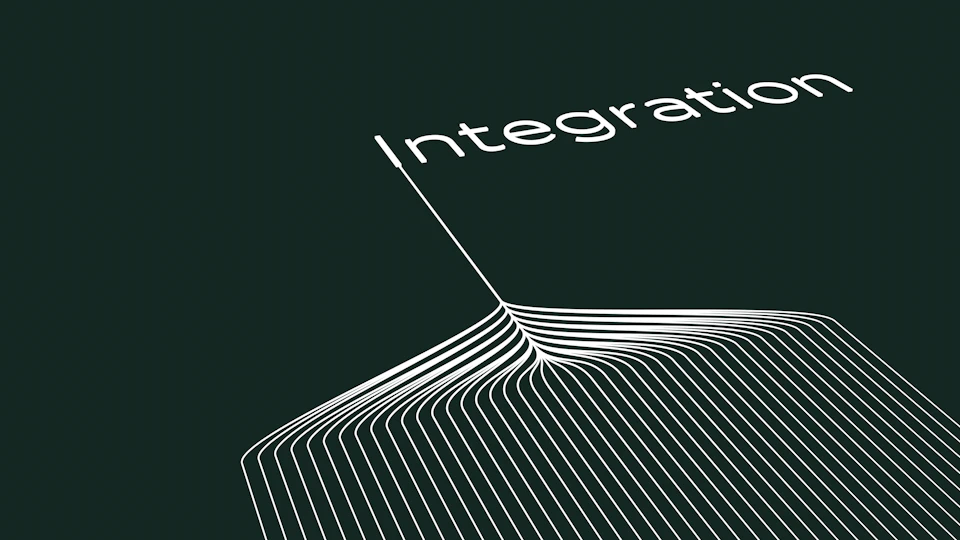
海外のfintechに詳しい知人から「便利な預金サービスがある」と教えてもらったのが、Raisinというサービスとの出会いでした。複数の国の銀行が提供する高金利の預金商品を、ひとつのアカウントで比較・申し込みできるという仕組みに、私はすぐに興味を持ちました。
企業評価額はすでに20億ユーロ(約3,262億6,000万円)を突破し、個人の貯蓄・投資スタイルに変革をもたらす存在として、投資家たちの視線も集まっています。
「誰もが簡単に、より良い利率で貯蓄・投資できる世界」を掲げるこのサービスが、今後の金融市場にどのようなインパクトを与えるのか。私自身の関心を込めて、改めてその可能性を深掘りしてみたいと思います。
400以上の銀行パートナーをもつフィンテック企業
Raisinは、ドイツ・ベルリンに拠点を置くフィンテック企業で、個人向けに高金利の預金商品や投資商品を提供する金融プラットフォームを運営しています。2021年6月には、同じくドイツのDeposit Solutionsと合併し、約400の銀行と提携、顧客数はすでに55万人を超えるなど、欧州最大級の預金・投資プラットフォームへと成長を遂げました。
私が特に興味を引かれたのは、Raisinを通じて、ユーザーがヨーロッパやアメリカのさまざまな銀行の商品を、ひとつのアカウントで比較・申し込みできるという点です。
たとえば、ドイツ国内の銀行が提供する金利が0.5%程度にとどまる一方で、ポーランドやバルト三国の一部の銀行では3~5%といった高金利商品が提供されているケースもあります。ドイツの預金者がより良い利率を求めて他国の銀行に資金を移そうとしたとき、通常ならば煩雑な手続きが必要になりますが、Raisinでは同じアカウントで各国の銀行に預けることができます。
この仕組みは、ユーザーにとっては高金利商品の購入が簡単になるというメリットがある一方で、銀行側にとっても新規の預金者を効率的かつ低コストで獲得できるという利点があります。つまり、利用者と金融機関の双方にとって、Win-Winの関係が成立するサービスなのです。
2024年の売上は前年倍増の約283億5,000万円
Raisinの資本状況、および事業拡大の推移について、みていきましょう。以下は、創業から2024年までの資金調達および売上高の推移をまとめた表です。
年度 | 資金調達額(累計) | 売上高(推定) | 備考 |
|---|---|---|---|
2013 | €1.5M(シード) | 非公開 | 初の資金調達ラウンド |
2014 | €6M(シリーズA) | 非公開 | 主要市場での拡大 |
2017 | €30M(シリーズB) | 非公開 | ヨーロッパ全域での展開 |
2019 | €100M(シリーズC) | 非公開 | 米国市場への進出開始 |
2021 | €170M(シリーズD) | 非公開 | Deposit Solutionsとの合併 |
2023 | €60M(シリーズE) | €158.5M | 初の黒字化を達成 |
2024 | 非公開 | $198.4M(約€183M) | 売上高が前年比で増加 |
2023年に売上高は€158.5Mで、初めて黒字化を達成しました。翌2024年には約$198.4M(日本円で約283億5,000万円)と前年からほぼ倍増しました。
このような業績の急拡大は、2022年以降の世界的な金利上昇が大きな追い風となっています。低金利時代には動かなかった預金者たちが、より高い利回りを求めて他国の預金商品に関心を持つようになり、Raisinの「金利比較と一括申し込み」という強みに注目が集まったからです。特にアメリカ由来の預金流入が急増し、提携銀行も拡大するなど、サービス全体の需要が高まりました。
政策金利の上昇 → 市場金利の上昇 → ユーザーが「より高い利率の預金口座」を求める → Raisinへの登録・預金が増える。→ 提携銀行からの手数料収入が増加 → Raisinの収益・資産規模が拡大と、極めて好タイミングで成長しています。
Raisinの今後のビジョン
私が今、Raisinの動向で特に注目しているのが、米国市場への本格進出です。アメリカの預金市場はなんと17兆ドル規模と言われており、Raisinにとってはまさに次なる成長の柱。この巨大市場への参入を、同社は重要な戦略のひとつと位置づけています。
その動きを象徴するのが、2021年に立ち上げた米国向けプラットフォーム「SaveBetter」です。すでに複数の銀行や信用組合と提携し、1億ドル以上の預金を集めたという実績を持っています。私自身、アメリカで国外のフィンテックがこれほど短期間で信頼を獲得できることに驚かされました。
さらに、RaisinはETFを活用した投資商品や個人年金プランなど、新たな商品の開発・提供が進められており、ユーザーが中長期的に資産形成できる環境が整いつつあります。こうした取り組みは、単なる預金比較サイトを超えた、総合的な金融プラットフォームへの進化を感じさせます。
たしかに、FRBが利下げに転じる場面では、一時的に高金利の魅力は失われる可能性があります。
しかしながら、定期預金の固定金利は一定期間有利に保たれるため、ユーザーが長期的に資金を留める可能性があることから、一定の収益維持は期待できます。
Raisinプラットフォームでは、ユーザーがいつでも短期 → 長期、あるいは逆方向に資金をスムーズに移動できます。これは利下げ局面でもユーザーに柔軟性と自律性をもたらす重要な機能も注目すべき点です。
また、Raisinの展開は個人向けサービスだけにとどまりません。グループ企業であるRaisin Bank AGを通じて、他のフィンテック企業や金融機関に対して、決済や貸付、本人確認といった金融インフラを提供するBaaS(Banking as a Service)モデルも展開しています。これにより、パートナー企業は自社ブランドでスムーズに金融サービスを立ち上げることができ、Raisinの存在感はBtoB領域でもますます高まっています。
米国でのプレゼンス拡大、商品ラインナップの強化、BaaS展開という三本柱が、Raisinをグローバル金融プラットフォームとしてさらに加速させている。私はそんなふうに感じています。
Raisinに対する主な批判・懸念点
Raisinのサービスは市場に高く評価されていますが、一方でいくつかの危険や課題も指摘されています。
まず第一に挙げられるのが、外国銀行への預金に伴うカントリーリスクです。Raisinでは、例えばエストニア、ポーランド、バルト三国など高金利を提供する銀行が多数掲載されています。しかし、これらの国々の中には、政治的・経済的に不安定な時期がある国や、金融システムが脆弱とされる国も含まれており、金融危機や経済混乱の影響を受ける可能性があります。
さらに、Raisinは各国の預金保護制度(通常10万ユーロまで)に基づいて安全性を担保しているとしていますが、この制度が実際にどこまで信頼できるかは国によって異なります。制度自体が存在していても、迅速な払い戻しが行われなかったり、国家財政がひっ迫して支払い能力が疑問視されるような場合には、実質的な保護が受けられないリスクもあります。また、意図せず多通貨運用や国際税務に巻き込まれる可能性も考えられます。
私の周りにも海外の預金を利用して、カントリーリスクが大きく下降して損害を負った人もいます。ユーザーは、金利が高いからといって安易に外国銀行を選ぶのではなく、その国の経済状況や信頼性を慎重に見極めた上で判断することが重要です。
日本でRaisin型サービスは少ない
現時点で、Raisinのアジア地域での具体的な展開計画はありません。日本にも複数の銀行の預金商品を比較できるサービスはありますが、Raisinのように同じアカウントで商品を購入・比較できるものは見当たりません。
その理由として、第一に日本では金融機関が預金を取り扱うために厳格な認可が必要であり、預金募集を行うには金融庁からの登録や免許が必要だからです。このため、Raisinのように複数国の銀行を取り扱うモデルは、規制上大きなハードルとなります。
次に、日本では欧州のような「オープンバンキング」制度が十分に整っていません。欧州ではPSD2(決済サービス指令)によって、銀行間のデータ連携が標準化されており、第三者プラットフォームでも簡単に銀行口座情報を活用できます。しかし日本では、銀行APIの整備が進みつつあるものの、いまだ金融機関間で足並みが揃っておらず、技術的な障壁が大きいのが原因かと私は推測しています。また、銀行法の規制緩和(特に複数行の代理・媒介を可能にする制度改革)も必要となってくるでしょう。
日本の預金金利は長年にわたり低水準で金利差も非常に小さいため、ユーザーが「預金先を選び直す」習慣がありませんでした。しかし、最近の金利上昇局面をうけて、日本国内でも高金利商品を求める動きが活発化しています。
ちなみに、私が提供するクラウドローンは、提携金融機関のローン金利を比較し、ユーザーがより有利な条件を選べる仕組みを提供しています。日本国内で「金利を比較して選ぶ」という意識を少しずつ根づかせるのに一役買っていると自負しています。
